学校が避難所になったら ~高校生が運営ゲームにトライ/大槌町
<ニュースエコー 2021年7月14日>
いつ起こるか分からない大災害。その時、学校が避難所になったらどうするか。東日本大震災で校舎が避難所になった岩手県の大槌高校で、生徒が避難所の運営をゲーム形式で学びました。
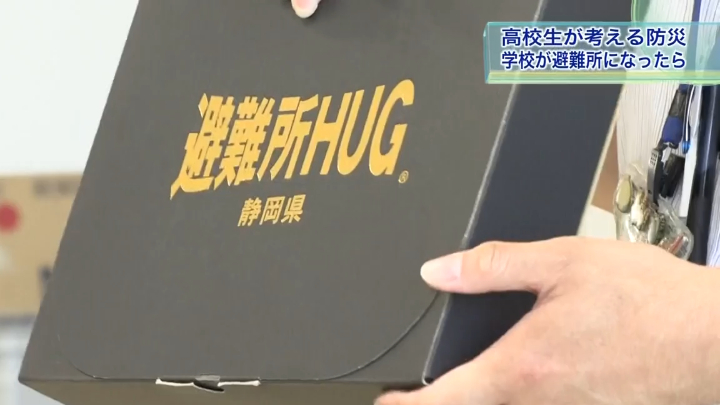
避難所運営ゲーム「HUG」とは?
「起立!気を付け!」
「よろしくお願いします」
(大槌高校復興研究会 松橋郁子教諭)
「避難所運営ゲームをしてもらおうと思って集まってもらいました。HUG(ハグ)といいます。みんなもどこに行っても災害があるかもしれいないので」
大槌高校復興研究会の生徒たちです。大槌高校は東日本大震災の2年後から、生徒たちが町の復興の様子を記録し、災害に強いまちづくりを考える復興研究会の活動を続けています。
先月30日、生徒たちは「避難所運営ゲーム」というカードゲームに取り組みました。頭文字をとって「HUG」と呼ばれるゲームは2007年に静岡県で考案されました。
(大槌町社会福祉協議会 渡辺賢也さん)
「皆さんそれぞれ、メンバーが避難所を運営する代表だと思ってください」
町の社会福祉協議会の渡辺賢也さんです。高齢化が進む中で社会福祉協議会は、震災以降住民の防災研修に力を入れています。
(大槌町社会福祉協議会 渡辺賢也さん)
「避難所運営は大人たちがやるものという認識があるかもしれないんですけど、若い力も組み込んで一緒に避難所運営というのをやってもらえたらいいなと思って」
避難所運営ゲームは1セット250枚のカードで構成されています。カードには避難者の年齢や性別、国籍に加え、心身の不調やペットなど、抱えているそれぞれの事情が書かれています。
さらに避難者の情報とは別に、避難所での発生が予測される様々な出来事を記したカードもあります。避難場所に見立てた平面図に避難者を誘導し、問題の対処を考えるというゲームをしながら、避難所の運営を模擬体験することができるのです。

臨機応変に対応 頼もしい高校生たち
大槌高校は東日本大震災で校舎の被災は免れましたが、避難所になりました。多い時で500人以上が避難生活を送る中、当時の生徒たちはトイレの水くみや駐車場の整理など、避難所の運営にあたりました。校舎は現在も町の避難所に指定されています。
次々とやってくるさまざまな事情を抱えた避難者を避難所のどこに配置するか。難しい判断を迫られます。
(生徒)
「最初は高齢者と小さい子がいるのを分けようとなったんですが、感染とかも繋がってくるんじゃないかとなって地域で分けようという話になって」
ゲームには町の職員も参加しました。
(大槌町の職員)
「女性93歳、男性66歳、3人来ました」
「高齢者どうしよう?高齢者どうする?奥の方がいいんじゃない」
町が期待しているのは子供たちや若い世代を起点に防災への関心が広まっていくことです。
(大槌町防災・協働まちづくり専門官 島村亜紀子さん)
「大槌はあれだけの震災を受けたので、やっぱり大槌の人は防災に強いと言ってもらえるような町にしたいと私は思っています」
臨場感を高めるため、カードにはないイベントが突然、発生します。
「明日の12時に総理大臣が避難所にきます」
(生徒)
「受け入れない受け入れない・・受け入れる、はなんで?」
「総理大臣が来るとなればマスコミも何社か来る。そのマスコミがテレビで報道することによってほかの地域に現状を伝えられる。支援を要請することもできればここにきている人の安否を伝えることもできる」
ゲームとはいえ、教室には緊迫した空気が漂いました。
(生徒)
「咳とか熱とか症状を持ってる人はどうするのかという対処とかにちょっと迷いました」
「避難してきた人をできるだけ安心させられるか考えながらできて、いい機会だったなと思いました」
大槌町と町の社会福祉協議会はこのゲームを自治会にも広げ、町全体の防災意識向上に役立てることにしています。