<ニュースエコー 2021年12月8日>
“てんでんこマラソン”と
防災教育/釜石市

岩手県釜石市の鵜住居小学校で、東日本大震災の際に子どもたちが津波から逃れた道をコースにしたマラソン大会が行われています。児童、保護者、地域の人たちにとっての大会の意義とは。そして、あの日津波から逃れた卒業生が訴える防災教育の大切さとは。
釜石市立鵜住居小学校。校舎は東日本大震災のあと、高台に新たに建てられました。津波避難場所に指定される校舎に続く階段にはオレンジ色のラインが引かれています。津波の際は必ずこの線より上に避難することをルールとしています。鵜住居地区は、東日本大震災で大きな被害を受けました。
(鵜住居小学校 堀村克利校長)
「てんでんこマラソン大会、『津波てんでんこ』の精神を忘れないようにしてほしいということです」
11月19日、この日は年に一度の校内マラソン大会でした。「てんでんこマラソン大会」の名前は、「津波が来たらとにかく早くてんでんばらばらに逃げろ」と言い伝えられてきた「津波てんでんこ」の精神が由来です。スタート地点は鵜住居復興スタジアム。この場所には震災前、鵜住居小学校と釜石東中学校の校舎が建っていました。
2011年3月11日、大きな揺れが収まると当時の児童・生徒たちは約1.5キロの避難路を走り、津波から逃れました。迅速な避難の背景には当時力を入れていた防災学習の成果があったと大きな注目を集めました。
(2020年1月 鵜住居小の児童)
「子どもから大人まで楽しめる防災訓練をして参加者を増やす工夫をしています」
防災学習への熱心な取り組みは、震災から10年を経た今も続いています。去年は6年生の児童が防災学習の成果を釜石市に提言しました。

マラソンコースはあの時の避難路 見守る保護者・地域住民は
4年前から行うマラソン大会も防災学習の延長線上にあります。
(鵜住居小学校 堀村克利校長)
「きょうのマラソン大会も走るという体力向上はもちろんですけれども、体で当時の避難した道を体感する、それをつないでいく、語り継いでいくという学習を展開しています」
児童は学年ごとの3つのコースで競いました。
「入ってきました、先頭入ってきました、手元の時計で5分8秒」
「最後まで!最後まで!」
(児童)
「(どんな練習をしましたか?)校庭をたくさん走ったりしました」
マラソンのコースは東日本大震災の際、当時の小学生が中学生と一緒に津波から逃れて避難した道です。沿道から保護者や地域の人たちが声援を送ります。
「がんばれがんばれ!」
「転ぶなよ」
(保護者)
「大きい地震が来れば津波も来る。高いところ、遠いところに逃げなくてはならないという認識は、子どもを通じて感じます」
子どもたちの活動は、保護者や地域の人たちの防災意識の向上に結びついています。
(地域住民)
「大きな災害があったときには自分の命を大切にするとか、(教訓を)風化させないということで、大きな意義があるてんでんこマラソンだと思う」
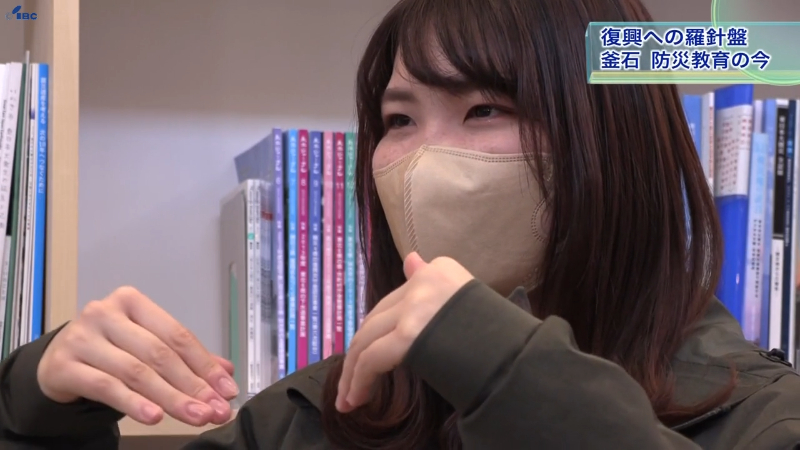
避難を経験した中学生が「語り部」に 進化続ける防災教育
釜石市の津波伝承施設、「いのちをつなぐ未来館」で“語り部”を務める川崎杏樹さん(25)。鵜住居生まれの川崎さんは小・中学校で防災教育を受け、実際に津波からの避難を経験しました。
(川崎杏樹さん)
「私たちは津波って何?みたいなところから始まっているんですが、今の子たちは自分の地域で起きた出来事という認識でしっかりと過去を振り返ってから、今できることをきちんとやろうという形になるので、もとの意識がすでに高い印象がある」
防災に関する講師も務める川崎さん、「災害を学ぶことは地域を学ぶことだ」と捉えています。
(川崎杏樹さん)
「地元のお年寄りから話を聞きつつ、ちょっとここは昔はねとか、地図は大丈夫って書いてあるけど昔の話を聞くと危ないかもとか、災害について知る、地域について知るということはいざというときに役に立つかなと思う」
てんでんこマラソン大会で今の小学生は何を学んだのでしょうか。
(児童)
「生まれて間もないころに震災がきたので、先輩方はここのコースを走って津波から逃れていった。もしあのような大きな災害があったときにはしっかり最後まで逃げて生き延びたいと思います」
防災教育は学校と地域をつなぐ懸け橋としての役割も期待されています。
(鵜住居小学校 堀村克利校長)
「さらに地域に開かれた鵜住居小学校にしていかなかればなりませんので、その部分では防災教育は大きな取り組みになっていくはずです」
大震災によって全国から注目を集めた釜石の防災教育は、今も進化を続けています。
(記念撮影をする児童たち)
「うのすまいー!」
×


