<ニュースエコー 2019年8月7日>
未来に生きる記録とは…
大槌町震災記録誌「生きる証」発刊/岩手
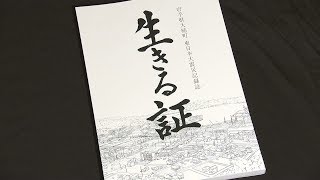
東日本大震災で、岩手県大槌町では過去の津波浸水域に建つ役場庁舎前に設置した災害対策本部を津波が直撃し、当時の町長を含む28人の職員が犠牲となりました。防災手帳のマニュアルに従って災害対策本部を高台にある中央公民館に設置していれば、防げた犠牲でした。
8月5日に大槌町が発刊した震災記録誌を基に、改めてあの時、役場庁舎で何が起きたのか検証してみます。記録誌では震災発生時の状況が克明に記されているため、VTRで当時を思い起こす方もいるかもしれませんが、検証報道に必要と判断し、そのままお伝えします。
今月5日に発刊された大槌町震災記録誌「生きる証」。沿岸12市町村の中で最後の発刊となりました。大槌町では過去2度の検証を行っていますが、災害対策本部の状況については十分に明らかになっていないと指摘されていました。記録誌では80にのぼる関係者や団体へのインタビューを通して、発災時から復旧・復興に至る大槌町の8年余りの歩みを町民自身の言葉で伝えています。
255ページからなる11章立てで、構成された記録誌の最終章は「忘れず、伝える」。災害対策本部が津波に襲われ職員28人が犠牲になった旧役場庁舎での出来事について、22ページにわたって綴られています。今回の記録誌発刊にあたり、大槌町の平野公三町長は次のように述べました。
(平野町長)
「あの当時何があったということをきちんと伝えることが必要だろうという思いで、この項目を立ち上げさせていただきました」
旧庁舎やその周囲で助かった役場職員、消防署員35人に改めて行われた聞き取り。証言者、犠牲者ともにほとんどが実名で、記されているのは記録として重要な意味を持ちます。加えて、一つ一つは断片的な聞き取り内容を、「いつ」「どこで」=時間軸と空間軸に沿って編み直したことで、あの時何があったのか、これまで分からなかったことが明らかになってきました。

強い揺れに思わず外へ
記録誌には、発災当初、強い揺れに混乱する職員達の様子が記されています。
(朗読)
「激しい揺れに驚いて庁舎前に駆けだすと、アスファルトが靴底の下で豆腐のように波立つのを感じた。」
「庁舎は倒壊する危険がある。戻るな、出ていろ。」
津波に対する危機感以上に、「強い揺れ」と「老朽化した庁舎」への不安が現場を覆ったと考えられます。それぞれの立場で、どんな心理で、どんな行動をとったのか?一人一人の証言と災害対策本部の様子を撮影した写真から、当時の様子が立体的に浮かび上がってきます。地域防災学を専門とする岩手大学の齋藤徳美名誉教授は記録誌の意義をこう考えます。
(齋藤名誉教授)
「今回初めて時系列にどんなことが起きていたか、目に浮かぶような記録が出てまいりました。これは非常に大きな前進であろうと、率直に評価したいと思います」
その後、旧役場庁舎前には長机などが出され、災害対策本部設営の準備が始まります。記録誌によると、災害対策本部長である当時の加藤宏暉町長と副本部長の東梅政昭副町長の2人は、発災時ともに町長室にいながら災害対策本部の場所や運営について言葉を交わしていなかったと記されています。
動揺する現場とリーダーシップの不在。「適切な避難行動」「住民への避難指示」、そのどちらもできないまま災害対策本部は迷走を続けます。そして…。

命を分けたのは…
(朗読)
「『津波だ!』寒空を切り裂くような叫び声が一帯に響いた。庁舎前から見えるはずのいつもの町が見えない。『黒い壁』のような大津波が立ちはだかっていた。」
(平野町長)
「東側の所に固まっているグループもいたんです。机を並べてあれが壁になっちゃったんですよ。」
津波が襲来する6分ほど前の災害対策本部を撮影した写真です。長机をぐるりと囲むように職員が立っています。中央棟玄関から入ればそのまま屋上に繋がりますが、東棟玄関から入ると遠回りになってしまいます。
(平野町長)
「机を挟んで東側の人たちと逃げる動線が違ったということになります。」
津波襲来時にいた場所がその後の運命を左右したのです。中央棟玄関近くにいた平野町長はいち早く屋上へ。
(朗読)
「(ドアを)開けてみたら眼下は海だった」
貴重な証言と丁寧な編纂で浮かび上がったあの時の様子。一方で、齋藤名誉教授は今回の記録誌がゴールではない、と訴えます。
(齋藤名誉教授)
「何がまずかったか、どうするかということを、改めてこれを出発点にして検証し、次に生かすことが必要なのだと私は思います。」
震災発生から8年が経過する中で初めて形となった、あの時の辛い、悔恨の記憶。それを未来の教訓に変える取り組みが、今後、求められます。
×


